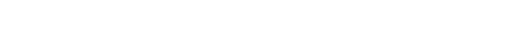ほしをすくうひと
当麻はときどき、少年のような顔をして少年の仕草をする。
夜空の星にふれたいと願うように、手を伸ばすのだ。
それは、きんと冷えた、寒い冬の夜に限られていた。暖房も部屋の照明も切る。作業用のパソコンの類の電源も落としてまるで儀式のように部屋を真っ暗にしてから、冬用のジャージの上に深い紺色のウインドブレイカーを羽織りベランダにでて、夜空に手を伸ばす。
伸はずっとこの仕草を不思議に思っていた。星の少ない都会の夜空なんてつまらないんじゃないだろうか、と。
気象庁の雪予報がすっかり外れ、綺麗に晴れた紺色の絨毯が頭上に広がった夜、伸は当麻に尋ねた。
「都会の星って少ないよね」
零度に近い空気が寒いというより痛いほどだった。それでも当麻はかまわずベランダに出て夜空を見上げている。
「そうか?」
「当麻ってほら、宇宙とか好きじゃない。だから天の川や星雲がくっきりと見えるような星空が似合っているなと思ってね」
「確かに天文台でそういうのを見るのは好きだけどな」
指で弾けばキンと響きそうな夜空から視線を外さず、当麻は続けた。
「都会の星空だからこそできることもある。おやじに教えてもらったんだ」
当麻はそう言って手を伸ばした。当麻の手のひらの上に大きな星。つられて伸も手を伸ばす。一等星の大きな星。たったひとつしかない。
伸は目だけで当麻の横顔を覗いた。出会ったころの彼よりもずっと幼い笑顔が浮かんでいた。詳しくは話したがらないが彼の父は科学者だという。まだ小学生にもあがらないころ、その父の隣で、当麻は同じ笑顔を満面に広げて手を伸ばしていたのだろうか。
「世間じゃ確かに、ずいぶんと高い金をかけて満天の星空を見に行くらしいが、俺はもともと都会育ちだしな。こっちの星の方がしっくりくる」
当麻が手を下ろして伸を見た。無邪気な笑顔は消え、二十歳を越えた男性の貌が伸を見下ろしている。ただその目の奥底に、まだどこか幼さを隠し持っているように見えた。
「伸の実家は星が綺麗なんだろうな」
「昔よりは少なくなった気がするよ。こんな空気の冴えた冬の日は星がきらきらと輝いていて、海に反射しているんだ。幼いころ、星に手は届かないけれど海の上の星ならすくえると思って、こっそり夜中に海に入ったら散々叱られたよ」
「大阪ではそういうのを『阿呆』という」
「あのねえ……年上に向かってそういうことは言わない」
2人のかすかな笑い声がかさなり、真冬の昼下がりに飲むホットココアのようなぬくもりが満ちた。それからやさしい沈黙。冬の夜の祝福を堪能したあと、伸は言った。
「もう少し星が見られるといいんだけどな」
「星が少ないわけじゃない。ただ見えないだけだ。見えるのは一等星かそれ以上。だからこうして手を伸ばすと」
再び、手を伸ばす。大きな青白い星が当麻の手のひらにおさまる。
「輝きの大きい星だけすくってふれることができる」
確かにそうだ。伸は2度、目を瞬かせて夜空をじっと見つめた。ゆっくりと視線を移動させて、星の数を数える。両手で数えられるくらいのきらめきだけが、都会の夜に在ることを許されていた。空気の澄んだ田舎では、こうはいかないだろう。差し伸べた手のひらに、数えきれないほどの星々が降りてくる。
「こうして星にふれていると、宇宙の真理に近づけそうじゃないか」
真理。そう口にして夜空に手を伸ばす当麻の姿はとても綺麗だった。寝起きのひどい髪型や徹夜続きのあとの目の下のクマや、伸がいないとゴミの山にうずもれてカップラーメンをすすっている姿や、そんなあらゆる事象を超越して美しかった。いつか当麻が言っていた。人間が見る夜空の星の光は、数万年、数百万年、数十万年の過去の姿なのだと。そんな星々に意思があるのなら、ちっぽけな人間よりも真理を知っているかもしれない。その光をすくう当麻の美しさは、24時間という時間と世間の常識の奴隷という立場から解放された、宇宙規模の時間で生きているからこその美しさなのだと伸は思った。
「伸、俺のこと、ちょっとバカにしただろ」
「そんなことないよ。君らしいと思ってさ」
喉を鳴らして笑い、伸は星を見上げた。夜空でひときわ大きな星が揺れていた。きっとあの星が生まれたとき、人はまだいなかったのだ。そういうことを、当麻は意識しないで知っている。だから彼はきっと天空の鎧に選ばれたのだ。
「僕にはたどり着けない深淵な真理だなって思っただけだよ」
「そうか? 真理なんて言うやつの言葉は間に受けちゃいけないな」
「君ってやつは」
ぬくもりをさえぎって、マイナス1度の風がよぎった。伸がくしゃみをして肩をすくませると、ふわりとウインドブレーカーにつつまれた。真理という言葉のもつ冷ややかさとは真逆のあたたかさが、伸の体温と鼓動の速さをほんの少しあげた。
「戻るか」
振り返って部屋に戻る当麻に、伸は思わず声をかけていた。永遠に終わらない真っ白い冬の映画が、唐突に幕を下ろした、そんな気分になったのだ。
「もういいのかい?」
「星はいつでも見られるしな」
そう言って、当麻は星に手を伸ばすように、伸の頬に手を伸ばした。星のあかりを灯したような淡いぬくもりが伝わる。冬特有のなにものにも代え難く言葉にすらできない感情が伸の心にあふれていく。冬の夜の寒さはあまり好きではないけれど、このあたたかさをしあわせと言うのだ、と伸は思った。
冒頭の一行と、今年の冬の寒さから浮かんだお話です。続きはブログで〜